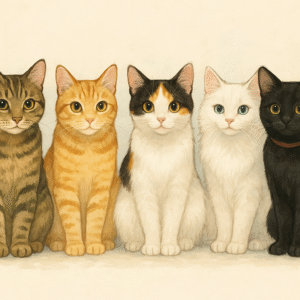初心者向け:自宅でできる!オリジナルポストカードの作り方
Contents
はじめに
「自分でポストカードを作ってみたい」と思ったことはありますか?
例えば、
「うちのネコたちのポストカードを作って飾りたい」
「孫たちのポストカードでおじいちゃんおばあちゃんに挨拶をしたい」
あるいは、
「オリジナルのかっこいいポストカードでお店の宣伝や告知がしたい」
という方もいるかもしれません。
そんな方に向けて、自宅で簡単にオリジナルポストカードを作れる方法をご紹介します。
今回は私が実際に自宅やってみた方法をメインにまとめています。
私は、イラストをポストカードとして商品化し、イベントやネットで実際に販売しています。
必要なもの、手順、費用、注意すること、失敗したポイントなどを私の経験を元にご紹介します。
これからオリジナルポストカードを作ってみようとしているあなたの参考になれば嬉しいです。
どんなデザインでもOK!まずは絵や写真を用意しよう
ポストカードアイディア
今この記事を読んでくれているあなたには、おそらく既にポストカードにしたいイラストや画像があるのでしょう。
どんなデザインでもOKです!
- 好きな写真
- イラスト
- コラージュ
- スマホの中の画像やデータ
ただし、商標登録されているものや著作権のあるものなどは、注意が必要です。
ここでは「あくまで個人で楽しむ範囲で」という前提のもとに進めています。
また、写真の場合で人物が入っている場合は相手の了承なく使用するとトラブルになることもあるので要注意です。
自分で撮影した写真や、描いたイラストなどのオリジナルの作品が最もオススメです。
ですが、「オリジナルデザインなんて、ハードルが高いわ…」と落ち込むことはありません。
写真やイラスト素材のフリーサイトなどもインターネット上にはたくさんあります。
これらを利用することで、問題なく素敵なデザインを完成させることができるはずです。
また、有料のサブスクリプションで使い放題のものや、1点ずつ買い切りのものもあります。
もし、迷っているのならば、一度チェックしてみるといいかもしれません。
私が素材を提供している無料イラスト素材サイトのリンクを貼っておきますので、よければ覗いてみてください。
illust AC (商用利用もOKな無料イラスト素材サイト) イラストレーターTsukimiのプロフィールページ
サイズについて
ポストカードのサイズは(100mm × 148mm)です。
実際にポストカードを作成するにあたり、デザインのサイズをポストカードのサイズに合わせる必要があります。
これは、実際にプリンターで印刷するための設定にも影響するのでとても大切です。
画像のデータが大きすぎると、データの一部だけが拡大されて印刷される、ということもあります。
なので、必ずポストカードサイズで作成しましょう。
サイズ変更は、イラストソフトや画像作成アプリを使うと良いでしょう。
無料の範囲でも十分に高機能で感覚的に使えるアプリCanvaは私も使っています。
誰でも簡単にデザインができる無料ツールCanva
データ(解像度・サイズ)について
ちなみに、解像度やカラーモードにあまり詳しくなくても大丈夫です。
解像度とは、簡単に言うと、「画像のきめ細かさ」です。
- 解像度が高い=きめ細かくてキレイ
- 解像度が低い=ぼやけたり、荒く見える
印刷では、「dpi (dots per inch)」という単位で解像度を表します。
ポストカードとして最低限キレイに仕上げるためには「300dpi以上」の解像度があると安心です。
データの大きさで言うと、「1748ピクセル×1228ピクセル」以上が目安になります。
「解像度って何?わからん、もう寝る!」という方は、イラストソフトや画像作成アプリのサイズ設定画面で『印刷用』を選べばOKです。
ソフトやアプリのツール側がちょうどよく調整してくれます。
既出のオススメアプリCanvaでも、もちろん可能です。
「色や仕上がりにとことんこだわりたい!」
「販売用にクオリティを上げたい!」
という方は、高解像度のデータを業者に依頼して印刷する方が希望通りの仕上がりになりやすいです。
印刷について
印刷に必要なもの
- プリンター
結論から言うと、私は家庭用のインクジェットプリンターを使いました。
パソコンと繋いだり、スマホとWi-FiやBluetoothで通信をして直接プリントできるものが便利です。
最近のプリンターは無線でも通信できるものがほとんどですので、よほど古いものでなければ問題なく使えるはずです。
ちなみに、私が使用しているプリンターはCanon PIXUSシリーズの4年前のものです。
現行機はこちら、ご参考までに↓↓↓
キャノン PIXUS TS5430BK インクジェットプリンター - 用紙
無地のインクジェット対応ポストカード用紙(白無地)です。
プリンター用のポストカード用紙は文具店、家電量販店、通販などで手軽に手に入ります。
枚数に対してお値段が少々割高にはなりますが、百均にもあります。
○マット紙(表面がサラッとしています)
白色両面無地ハガキ(100㎜×148㎜)国産上質紙135㎏【250枚】【500枚】【1000枚】
たくさん印刷したい方は1ロットの多いものをまとめ買いすると、1枚当たりの単価が下がってお得です。
マット紙のサラッとした質感と反射しない紙質がディスプレイに向くと思うので、個人的にオススメです。
○光沢紙(表面に光沢があってツルっとしています)
はがき【プレミアフォト光沢】30枚 インクジェットプリンター専用ハガキ
こちらは小ロット30枚なので、お試しにちょうどよいです。
『郵便はがき』や郵便番号のフレームが既についているので、すぐに郵送できます。
光沢紙は写真を印刷する際に美しい仕上がりになります。
自宅で印刷することで、少部数でも手軽に試せるのがメリット。
印刷の発色も良く、自分で調整しながら印刷できるのも便利です。
印刷設定
- サイズ設定
印刷する時にサイズ設定を行います。
お使いの機器にもよると思いますが、パソコン(スマホ)側とプリンター側の両方が『はがきサイズ』の印刷になっていることを確認しましょう。
はがきのサイズは(100mm × 148mm)です。 - 部数の決定
最初は1部ずつ試し刷りをしてみて確認をします。
⇒上下左右にずれていないか、発色はどうか、不自然な箇所はないか、など。 - 印刷のクオリティ設定
せっかくオリジナルポストカードを作製するのですから、最高品質の印刷設定にしましょう! - 印刷後
しっかりと乾かす。
すぐに触るとインクが滲んだり、重ねることでインクや用紙特有の臭いの原因になります。
自宅印刷のメリットとデメリット
さて、ここまで、自宅で手軽にオリジナルポストカードを作る方法についてお話してきました。
実際に私は自宅で自力で作成しているわけですが、「なぜ印刷の専門業者さんに依頼しないの?」という疑問が湧くのではないでしょうか。
分かりやすくメリットとデメリットに分けて比較していきましょう!
自宅印刷にするか、業者さんに依頼するか迷っている場合は決断の一助になると思います。
【メリット】
- 1枚から作れる
- トータルのコストが抑えられる
- 慣れれば手軽
- 修正・変更もすぐできる
【デメリット】
- インク代・用紙代など別々にコストがかかってくる
- 印刷設定や紙選びに手間と時間がかかる
- 印刷クオリティは業者に比べるとはるかに落ちる
- 大量印刷には向かない
私も含めて、多くの方が気になるポイントを一言でお伝えします。
自宅印刷は『時間と手間はかかるが割安』
業者さんへの発注は『すごくキレイに仕上がるがお値段もそれなりにする』
時間と手間について言及するならば、自宅印刷ではデザインや道具選び、印刷設定を行い、印刷後に乾燥などの行程があります。
発注する場合には、提示された中から用紙や様式を選んだり、予算と相談したり、あるいは実際にやりとりする必要があるかもしれません。
かかる手間の内容こそ違えど、どちらにしてもそれなりに時間も手間もかかります。
仕上がりに関しては、圧倒的な差があります。
専門店はさすが専門店、明確に美しい仕上がりになります。
その分、割高感はありますが、『1枚~のハガキ印刷』をリーズナブルな価格で謳っている専門店もありますので、検討の余地は十分にあります。
自分の目的に合わせて選ぶのがよいと言えるでしょう。
やってみてわかった!ありがちな失敗と対策
- 両面印刷で上下逆さまになった
【対策】印刷前に向きを確認して用紙を挿入する - 印刷がズレた…
【対策】用紙をまっすぐにセット!セットするプリンターのガイド(ツメ)をきっちり合わせるのがコツ。 - インクが切れ状態で印刷して発色が悲惨
【対策】インク残量の警告が出たら、潔く交換。色むらが出ることもある。 - インクジェット用紙を使わなかったら色が沈んだ
【対策】普通紙やレーザープリンター用の紙だと、にじんだり色が沈んだりする。 - 印刷面をすぐに触ってしまい、指紋やにじみが…
【対策】印刷直後の印刷面には触れず、しっかり乾かす。特に濃い色の部分はインクが多く、光沢紙はにじみやすく乾きにくいので要注意。 - 画面の印刷の色が違ってがっかり…
【対策】最初の1枚は「テスト印刷」として考え、それを元に微調整して理想の色味に近づける。 - 裏面(宛名面)のデザインがギリギリすぎて、郵便枠や切手スペースを邪魔した
【対策】郵送を想定する場合は、日本郵便のガイドラインを確認すると安心。(次章参照) - プリンターの紙送りローラーが汚れていて、黒いスジが入った
【対策】ときどきクリーニングをしたり、裏紙の使用を控えるようにすると印刷トラブルを防げます。
新しい挑戦にちょっとした失敗はつきものです。
私がやった失敗だけを挙げてもこんなにありました。
しかし、印刷前に予めチェックをしたり、丁寧に作業を行うことでほとんどが防げます。
焦らず、怠けず、欲張らず…
他のことについても同じことが言えそうです…笑

郵送したい人へ:注意点と郵便ルール
- ポストカードとして送るなら「POST CARD」と書く必要あり
「郵便はがき」または「POST CARD」と書いていないと、「第一種郵便物」として84円〜になることもあるので要注意です。
一般的なポストカードは「第二種郵便物」として扱われ、現在(2025年5月時点)の料金は63円です。 - サイズと重さのルールあり(リンク参照)
ポストカード:148㎜×100㎜、6g以下
サイズが大きすぎたり、重すぎたり、厚すぎたりしても、第一種郵便物(つまり手紙)として84円~になる可能性があるということです。 - 詳細は日本郵便のガイドライン参照
POST CARDの表記について
サイズ・重さについて
手づくりポストカードの楽しさを、あなたもぜひ
いかがでしたか?
オリジナルポストカードづくりは、特別な道具や難しい技術がなくても、ちょっとした工夫とアイデアで気軽に楽しめる趣味です。
はじめは思うようにいかなくても、印刷やデザインのコツがつかめてくると「自分だけの作品を形にできる喜び」がきっと感じられるはずです。
身近な人への季節のごあいさつに。
イベントのちょっとした配布物に。
自分だけの作品集として並べてみても素敵です。
この記事が、あなたのポストカードづくりの一歩につながれば嬉しいです。
ぜひ気負わず、気軽に、まずは1枚から試してみてくださいね。
よかったらこの記事をSNSでシェアしてもらえると嬉しいです。
「こんな風に作れるんだ!」と誰かのきっかけになるかもしれません。
あなたの作品づくりも、ぜひ楽しんでくださいね。
※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。リンクをクリックして購入されると、私に報酬が支払われることがありますが、読者様の購入金額には影響ありません。